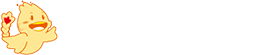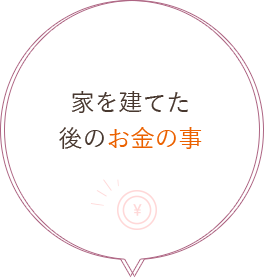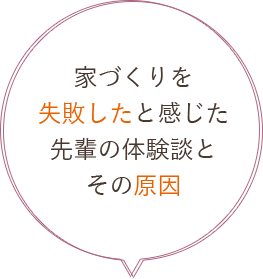Q & Aよくある質問
よくいただくご質問をまとめました
新着のご質問
- 可変防湿気密シートという物は、梅雨時期に壁全体から湿気が入ってきてしまうのではないかと思ったのですが、エアコンを上手く使えば、コントロールできる範囲のことなのでしょうか?
-
これも非常に微妙なところですね。夏型壁体内結露を起こしてしまうくらいなら、まだ室内に湿気を流入させた方が良いと思いますが、それでも暑い時期には1日に1リットル~の湿気流入が起きる可能性があります。26℃60%程度の環境で良ければ、そんなに気にしなくても大丈夫ですが、夏に40%台の湿度をと考えると、可変防湿シートが少しネックになってきます。どんな室内環境を作りたいかどうかで、最適な壁体構成も変わってきます。
- 凰建設さんは大工育成型?それとも傭兵型?
-
これで弊社が傭兵型だったらちょっと残念ですよね。凰建設は60年前の創業時から一貫して新卒大工さんを採用し続けている会社となります。弊社の大工さんの平均年齢は28.8歳です(2020年現在)
一番若い大工さんで19歳です。
- 一種のダクト式換気で、OAに電子集塵機をつけている事例を見かけるのですが、集塵機があるとダクト清掃や熱交換素子交換の頻度は下がるものですか?
- はい、下がりますね。
はい、下がりますね。ただし、電子集塵機の本当に必要な地域なのかどうかはちょっと考えてみてください。
田舎の空気が綺麗なところであれば普通のフィルターで十分ということもありますので。
- 内と外を繋ぐためにデッキを作るという話をよく聞くのですが、デッキを作る以外に良い方法はありますか?
- 外と内をつなぐための伝統的な空間が「縁側」です。
外と内をつなぐための伝統的な空間が「縁側」です。私が思う最も良いのは縁側の内側が断熱気密ライン、縁側は外という形で作っておき、夏冬それぞれの気候に備える事だと思います。
庇を2m程度伸ばして空間を作るだけでも非常に良いつなぐ空間になるかと思います。
- 土地選びにおいて重視していること、外せないことはありますでしょうか。
-
災害リスク、人口が減少していないことは気にしておかなければなりません。
またもう一つの観点として、将来的に自分が管理すべき不動産を増やさないという事です。両親祖父母は勿論、親戚筋から、将来自分が相続することになりそうな土地がある場合は要注意です。
核家族化少子化が進み、思わぬところから土地や建物を相続することも起こっております。そのような土地がある場合は、今の時点で新たに不動産を購入することはよくよく検討した方が良いです。その土地に家を建てたほうが、何年か待ったとしても生涯で家や土地に使うお金は少なくて済むことが多いです。
- 小屋裏エアコンだけで全館冷暖房することが出来る会社もあると噂で耳にしました。本当にできるものでしょうか?
- きちんと設計ができていれば大丈夫なのですが…
床下エアコンの冷気を小屋裏に送り込むやり方があるのと同様に、小屋裏エアコンで作った暖気を床下や1階に送り込んで暖房をするやり方も存在します。きちんと空気のエネルギー差の設計が出来ていればそれは大丈夫なのですが、きちんと出来ていない例の方が多いですね。
- アメリカカンザイシロアリの被害が拡大している様ですが、新築時に何か対策をされていますか?
-
これは厄介な問題ですね。現在の所、気にされる方は全棟ホウ酸処理を勧めるという形になります。建物を建てる際には様々なリスクを天秤にかけて予算の使い方を決めますが、質問者さんにとって、カンザイシロアリのリスクがどの順位に来るかによって、予算が回る/回らないを決められたら良いかと思います。
恐らく日本で一番白蟻の事を研究している京都大学の吉村教授は、外来種であるカンザイシロアリの対策は、根絶させる事であり、地域自治体全体で取り組まなくてはならないと言われております。マクロな話をすると、これ以上アメリカから木材や古家具を輸入しないというのが、最も現実的な対策になります。つまり、国産の木材を使って家を建てるという事が、まわりまわってカンザイシロアリの撲滅につながります。
- 耐震等級3、高気密高断熱にすると一階の南側窓面積が小さくなると聞いたことがありますが本当ですか?
-
本当です。窓は断熱的にも耐震的にも弱点になります。無制限に窓を付けて耐震等級も3が取れるという事はありません。特に、南北に長い建物になる場合は、1階の南側の窓は思うように取れないことが多いです。
高気密高断熱にする事と、窓が小さくなることは関係がなく、耐震等級3を取ることだけが窓の大きさに関係してきます。
ただ、この手の話が、間違って伝わりやすいのは、質問者さん含めて殆どの方が、数字を入れずに話をするからです。例えば、南の間口7mに対して、耐震等級2であれば窓部分が4m壁部分が3mのバランスが可能だったのが、耐震等級3にすると、窓部分が3m壁部分が4mのバランスになりますなど、具体的な数字を入れないで「大きくなる、小さくなる」「思うように窓が取れない」という定性的な話をしてしまいますと、答えている人は、全面ガラス張りは流石に無理というイメージで話しているけども質問している人は、人の頭も出ないような窓しかつかないと受け取っているなどの齟齬が生じます。
具体的な質問には具体的な答えが返せます。抽象的な質問には抽象的な答えしか返せません。
質問者さんが思う南側の窓の大きさが分からない以上、答える側としては安全側を見て「窓は取れない」と答えるしかありません。
- 床下自主点検のために基礎の高さは何センチ以上必要でしょうか?
- 長期優良住宅のルール上は床下の空間は有効で300mmの高さが必要となっております。
長期優良住宅のルール上は床下の空間は有効で300mmの高さが必要となっております。しかし、住まい手の方が自主点検で潜るとなった場合、体格によっては300mmでは通れないという事も発生致します。床下をしっかりと点検できるものにしようと思うと、有効で600mm程度(ダイニングテーブルの下の空間くらいの高さ)があった方が良いです。しかし、今の日本の家づくりでそこまでの空間を作る事は、非常に稀です。
将来的には床下空間の高さもどんどん高くなっていくのではと想像しております。
- 長く使える円形のダイニングテーブルを探しています。おススメのメーカーはありますか?子供がまだ小さいので、木工製品だとすぐに傷つきますでしょうか?
-
ダイニングテーブルですね。
お勧めのメーカーも、何を求めるかによって変わりますが、是非お勧めしたいのは、飛騨産業さんはじめとする、岐阜県は飛騨高山の家具になります。
ちなみに、傷が付くのが嫌であれば木工製品は選ばない方が良いです。
金属脚にガラス天板を組み合わせたほうが余程傷が付きにくいです。
しっかりしたものを買って、傷や染み等も含めて愛着を持っていただき、世代を超えて使うくらいの心のゆとりがないと安物買いの銭失いになりかねません。
毎年バーベキュー用の折り畳みテーブルセットを買い換えれば、定期的に全く傷の無いダイニングテーブルになります。極端に言えばそういう事です。