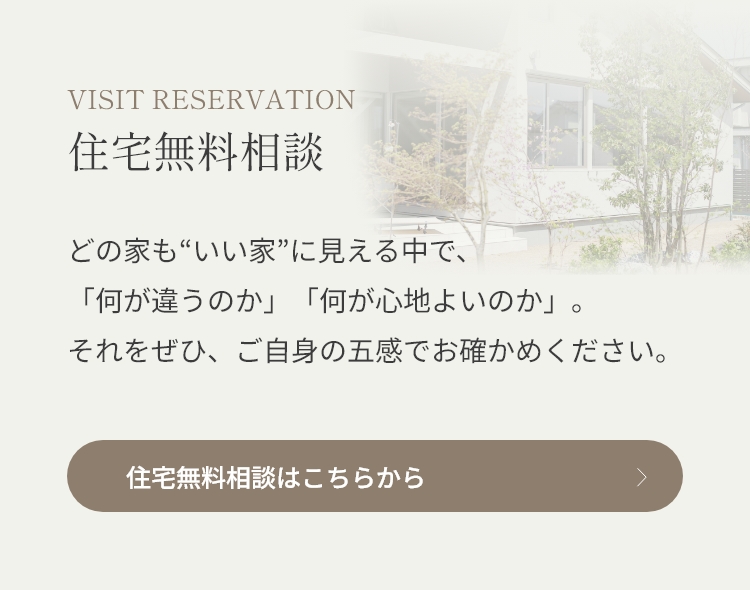QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期優良住宅認定と性能評価認定は取得していますか?
-
長期優良住宅と建設性能評価は標準で全棟採用しております。
- 自己資金はどれくらい必要ですか?
-
設計申込の際に50万円(税抜)をお預かりします。住宅ローンを組むには自己資金が1割程度は必要だと言われますが、資金についてのご相談も無料住宅相談で承っております。
お申し込みはこちら→https://www.ohtori.net/reserve/
- 凰建設で建築した場合、構造計算の計算書を頂くことは可能でしょうか。
-
はい、可能です。構造計算や断熱計算など、全ての書類は引き渡し時に住まい手にお渡ししております。許容応力度計算の書式などは数百ページに及びますので、けっこう嵩張ります。しっかり保管していただければと思います。
- 土地は探してもらえますか?
-
ご希望であれば、不動産部門の担当が土地探しから買付けまでお手伝いさせていただきます。ご希望の土地をお探し致しますのでご相談ください。
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
これまでにいただいた質問
- 打ち合わせに子供を連れて行っても大丈夫ですか?
-
キッズコーナーもご用意しておりますので、ぜひご家族でお越しください。
- 建売のような性能が比較的低いであろう物件であっても、築20年以内で劣化が少なければ新築よりもコスパ良く高性能な物件が可能なのでしょうか?耐震なども考えると、逆に新築よりもあるいは新築並みに費用がかかるので新築の方が費用的にも良いということにはならないでしょうか?
-
耐震等級3を目指すと、かなり大掛かりな施工になりますので、難しいかなと思いますが、現行の耐震等級1かつ断熱をG2グレード程度にという事でしたら、築浅の物件をリノベした方がコスパ良くできる可能性が高いです。勿論、インスペクションをして、構造自体の劣化が無いか、補強不可能なダメージが無いかを調べてみるのは必須です。
デメリットとしては、やはり設備や間取りが新築の様に自由にならないという事ですね。
- リフォームの依頼はどのようにしたらいいですか?
-
まずは電話またはHPの無料住宅相談からお問合せくださいませ。リフォームや増改築は実際に現地を拝見させていただいてから御見積を提出させていただきますので、ご都合の良い日時にお伺いさせていただきます。
- 築4年、Ua値0.4でC値0.3の第三種換気の家に住んでいます。築後に付加断熱の良さを知り、リフォームで付加断熱を追加することを検討しています。外壁がガルバのためリフォームのために剝がすのはもったいない気がしますが、どうなんでしょうか?
-
その断熱性能であれば、ガルバのメンテナンス時期になるまではそのままでも良い気がします。
どちらかというと外壁よりも内装の寿命の方が早く来るかと思いますので、内付加断熱を検討する方が良いのかもしれません。
- 森さんの「子供たちに社会に負の遺産にならない家を残そう」という考えにとても共感しています。今、私自身は長期優良住宅の木の家で暮らしていますが、平成2年築の某HMの軽量鉄骨の家も保有しております。この家を直して住む価値があるのか悩んでいますが森さんならどうお考えになりますか?
-
難しい質問ですね。旧38条認定によって建てられた建物だと思いますので、当時建てたそのHM以外の建築会社だと、手をつけようとしない可能性が高いです。そのHMに相談したときに、直す相談に乗ってくれるかどうかは聞いてみないとなんとも言えません。旧38条認定や型式適合認定の建物が生みの親(建てた建築会社)に見放されると、そのまま住むか、壊すかという選択肢しか無くなってしまいます。一縷の望みをかけて、建てた会社に聞いてみてくださいませ。