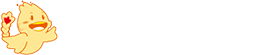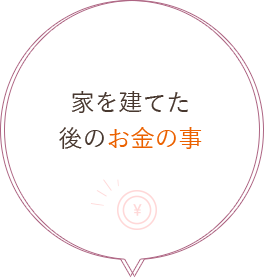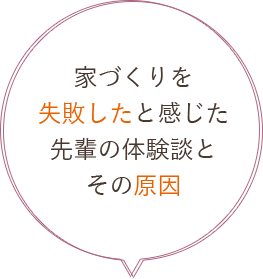Q & Aよくある質問
よくいただくご質問をまとめました
新着のご質問
- ガルバリウム、トリプルガラスの窓を利用している場合、携帯電話の電波が悪くなると思うのですが、どのような対処方法がありますでしょうか?森さんはどのように対処されてますでしょうか?
- 外壁を金属の物質で覆うほどに携帯電話の電波が通りにくくなる問題はよく聞きますね。最も簡単な解決策は、屋内のWi-Fiをしっかり整備する事だと思います。近年既に電話を掛けるというシーンは少なくなり、携帯電話と言えどもWi-Fiにしっかり繋がってさえいれば不便を感じるシーンは殆ど無いかと思います。どうしても携帯電話の電波を強力にしたいという事であれば、仰るように小型の基地局を家庭内に設置するというのが王道の解決方法になるかと思います。
- 熱負荷計算の中の顕熱計算のうち、外皮の熱とサッシからの熱は被ると思うのですが日射を別計算にするのはどういう理由でしょうか?
-
ガラスを透過した太陽光線が床などに当たるとそこで熱に変わりますので、外皮やガラスの断熱性能とは別に、日射による取得熱を計算しないと辻褄が合わないことになります。
- メルマガを拝読しているうちに、LCCM住宅への興味が湧いてきました。建材、納まり、仕様、設備、敷地選び、住まい手の維持管理など、LCCM住宅の建設にはどんなポイントがあるのか、教えていただけないでしょうか?
- LCCM住宅は、建設から運用、解体までのトータル期間でCO2排出量がマイナスになるという住宅になります。省エネルギー性は勿論の事、生産時に発生するCO2も減らしていくことが望ましいとされます。鉄骨やコンクリートよりは木材。木材でも集成材よりは無垢材、人工乾燥材よりは天然乾燥材を使った方が、生産工程でのCO2排出は少ないので、LCCM住宅になり易くなります。断熱材も、出来るだけ自然由来の物を使った方が生産時のCO2排出量は少ないので、そういう物を使うと良いです。また、建設時と解体時の排出が相当なウエイトを占めますので、なるべく長い期間、建物が存続し、太陽光発電などでエネルギーを創り続けるほうが有利になります。ポイントをまとめると、なるべく自然に近い素材で家を建てる。なるべく省エネな家を建てる。なるべく家を長持ちさせる。なるべく創エネ設備を沢山つける。となるかと思います。設備についても同じ考え方で、長く使えるもの、メンテの容易な物を選ぶと良いかと思います。維持管理は直接的にLCCMには関係ありませんが、住宅の寿命を縮めるようなスパンで放っておくような事は避けていただきたいと思います。
- ダクトレス第3種換気の場合に気密を取った場合、風圧がプロペラファンにモロにかかるのでカタログスペックの最大風量で換気計画を立てると換気回数が足りなくなりますか? また風速は常に2〜3mあって、そうなると9-10Paの風圧がかかることになりますがこれも最初から考慮した方がいいでしょうか?
- カタログスペックよりは換気量が落ちると思って設計して良いですが、そういう事も諸々ひっくるめて、換気回数0.5回という、余裕を見た計画になっておりますので、わざわざ増やすという事をしなくても、結果的には丁度良くなることが殆どですので、そのまま設計しても問題ない事が多いです。夏季、冬季で1階2階の給排気口からの流入/流出量が変わる事まで考慮して計画をしたいという事であれば、計算に入れてみるのも面白いですね。
- 「長期優良住宅」の「保全計画」についてなのですが、何千万円も維持管理に必要なモノでしょうか?1万円/月×30年で360万円、2万円/月なら720万円とかなりの金額に感じます。 また、「保全計画」以上に長持ちして計画変更が必要な場合、その手続きは面倒なものなのでしょうか?
- 本気で100年以上家を持たせるのであれば、30年で360万円であればかなり安い方、720万円であれば妥当な所というのが実績に近い数字かなと思います。構造が長持ちして計画を変更する際の手続きは、勿論手間がかかるものにはなります。その金額を何と比べるかだと思います。30年後に解体してもう一件家を建てるのであれば、720万円などという金額で済むはずもなく、手続きの手間や申請にかかる時間やコストもリノベのそれとは天と地ほど違います。長期優良住宅というのは、3~4世代、住宅を住み継いでいく事を考えた時に、コストが最小になる事を考えて制度が設計されております。その考え方に理解賛同が出来ないという事であれば、長期優良住宅は重荷になってくると考えます。
- エアコン冷媒管、ペアコイルの保温材厚みについての質問です。 一般的には液管・気管両方とも8mmですが、高断熱タイプのもので気管が20mmのものがあるようです。 メーカーの主目的は結露防止だと思いますが、エアコン運転上の効率アップにも繋がるのでしょうか?
- 仰る通り、若干の効率アップにつながります。こだわるのであれば、断熱の厚いものを採用されると良いかと思います。ざっと計算してみると、配管長さが6m、冷媒温度が0℃、外気温30℃の時に20mm被覆で24Wの熱損失、8mm被覆で41Wの熱損失です。冷房期間中2500時間運転したとすると34kWhの差が生まれます。COP3.0、電力料金30円/kWhでエアコンが動いた場合、ひと夏の電気代の差は425円になります。
- 我が家では屋内の温湿度とCO2濃度は測っているのですが、最近ホルムアルデヒドを測っている方を見かけました。 ホルムアルデヒドをCO2と一緒に測れる商品はありますでしょうか?
- ホルムアルデヒドについては、弊社も測定する際は専門の方にお願いするようにしております。自分で測定するのであれば、検知管によるものが良いかと思います。卓上のデジタル温湿度計のようなもので、精度よく測れるものがあるかと言われると、非常に怪しいと思っております。ただ、簡易な物でも数万~十数万という金額になるのがホルムアルデヒドの測定器です。
- 洗面脱衣室の床材はどのようなものがオススメでしょうか? 無垢材を使うことは劣化のリスクが高いでしょうか。
- 私の自宅は厚さ40mm程の杉の無垢床、無塗装材を使っております。夏はさらさら、冬はひやっとせずに快適です。水が溜まったまま放置という状況が続くと良くないですが、あまり気にせず使っております。当然水染みなどはありますが、劣化しているという感じにはなりません。そういう事も含めて表情が変わっていく家を慈しむことができるのであれば、針葉樹の無垢床は大変お勧めになります。それが嫌であれば、水の浸みにくい素材が無難かと思います。
- 動画で配線問題について知りました。 木造ドミノ工法というものが設備交換に対応し易そうですが、普通の工法で配線胴縁を適用するのと、どちらが総合的に良いのでしょうか?
- 木造ドミノも構造をシンプルに出来る良い作り方だと思います。配線胴縁をする事と、ドミノは特に矛盾する事でもありませんので、ドミノと配線胴縁を両方採用することも勿論可能です。逆に言えばドミノと配線胴縁というのは対象としているメンテの部位が違うので(ドミノはマクロ、胴縁はミクロ)どちらかがどちらかを兼ねるという事もありません。
- 1階の南側の掃き出し窓にシェード・タープ用の金具を外壁に付けました。 この場合、それを貼るためのポールか何かを庭もしくはフェンスに付けたいのですが、そのような製品はあるのでしょうか?
-
フェンスだと、タープが風にあおられた時に持っていかれる可能性があるので気をつけていただきたいのと、フェンスの高さが低すぎてタープが使いづらいという問題が出てきます。最もコスパの良い商品は、昔の庭に置いてある洗濯物干し(コンクリートの重りにポールがついているアレ)をコンクリートの部分だけ埋めてしまう事ですが、ポール部分のデザインを塗ったり加工したりという手間も発生します。時間はかかりますが、丁度良さそうな所に庭木を植え、幹がしっかりしてきたらそこにタープを掛けるというのが良い感じでしょうか。勿論お金を出せば外構部材で各種垂直に立つポール部材は有りますので、それでも良いと思います。