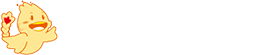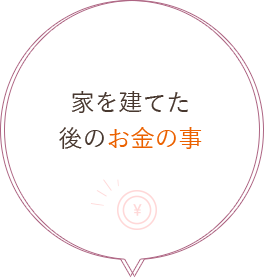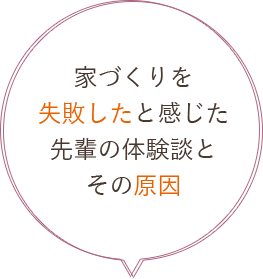Q & Aよくある質問
よくいただくご質問をまとめました
設計について
- 片流れや段違い屋根にする場合、雨漏りをしにくくするためには、どのようなことに注意して新築戸建を建てたら良いでしょうか?
-
軒をちゃんと出す事です。
- パッシブハウスジャパンの省エネ建築診断士の資格について質問です。 エキスパートやマイスターと言った記載があったのですが、どのような資格でしょうか? そのほか、工務店選びでおススメの資格はありますか?
- 省エネ建築診断士の資格には種類があります。試験の時の成績優秀者にはエキスパートがもらえます。5年後の更新の時に頑張るとマイスターがもらえます。合わせて、断熱系の民間資格はいくつかあります。・省エネ建築診断士(パッシブハウスジャパン)・暮らし省エネマイスター(Forward to 1985)・エネルギーエージェント(エネパス協会)・BIS(北海道建築技術者協会)等を持っている方は勉強熱心だと思います。日本に10人ほどしかいない、ミライの住宅主催全館空調設計講座終了証を持った人も非常に知識の深い人になりますのでお勧めです。
- ZEH5つ星ビルダーで新築してもらう場合、耐震等級3を取れていたら低性能な家になりにくいですか?
-
そんな事は有りません。
太陽光がどっさり載っているだけという家もありますので、基本的な断熱性能は気にした方が良いです。
- ガルバリウム鋼鈑は雨がかりしている方が汚れを落とせると聞いたことがあります。南面で日射遮蔽しない東西北面はガルバの場合、デザインのバランスがあると思いますが、軒をださない方が良いのでしょうか?
-
どの地域に建てるかにもよります。沿岸地でなければあまり気にせず使って大丈夫です。
- メンテナンスコストを考えますと、屋根、外壁、樋の素材をガルバリウムに合わせるなどすることが生涯コストを押さえることにつながりますか?この場合、漆喰などは耐久性が異なるため混ぜるな危険でしょうか?
- 素材を合わせるのはメンテナンスコストを抑えるためには有効です。ただ、壁は漆喰、屋根はガルバなど、影響の少ない混ぜ方もありますので、絶対にやってはいけないという事はありません。屋根材の耐久性の方が上に乗る太陽光パネルよりも短いなどの例が、混ぜるな危険です。外壁の耐久性よりも、外壁にくっつける設備品の方が長持ちするというのも残念な例になります。
- 屋根の通気を二重垂木工法でとる場合、1層目のルーフィングはタイベックルーフライナーで、屋根材側の2層目のルーフィングはアスファルトルーフィング940でも問題ないと聞いたのですが、本当でしょうか?
-
弊社は1層目に透湿防水シート、2層目の上に断熱吸音版を貼ったうえで改質アスファルトルーフィングを使っておりますが、実はそれでも諸外国の仕様に比べるとまだまだ至らない構造です。
耐熱性の改善を謳ったのが改質アスファルトルーフィングではありますが、黒いガルバの熱を長年受け続けるとやはり劣化します。家の耐久性は、ボトルネックから順番につぶしていくことが大事です。どこか1つだけ、永久に持つような素材を使っても、別の所にボトルネックがあれば、ネックの素材の耐久性になってしまうか、メンテの頻度が上がっていきます。トータルバランスを見ることが大事です。
- 太陽光を載せる検討をしています。 オール電化、4kWと仮定して、全て売電と昼間にエコキュートのどちらがオススメですか? また災害に備えて自家消費用のコンセントをつける場合、エアコン、冷蔵庫の両方に着けておけば安心ですか?
- 売電、買電共に電力契約によります。そして最も大きな要素は、どれだけ普段電気を使うかという事になってきます。それによって答えが違います。非常用電源は冷蔵庫優先をお勧めします。家の性能が高くないとエアコンは200Vになりますので、使えない場合も多いですが、パワコンが2つあって回路が余るようであれば100Vのエアコンに非常用コンセントを取り付けても良いと思います。
- 高気密高断熱の家は反響しやすくなるというのは本当でしょうか? もしピアノなど楽器を弾くことを想定する場合、対策など必要でしょうか?
- 外に出ていく音が無くなる分、反響して中に入ってきますので、反響しやすくなるのはその通りです。反響したくないという事であれば、内装をなるべくふわふわした素材の物に近づけると良いです。反響音が少なくなります。
- とあるパンフレットに、2Fの渡り廊下(吹き抜けを横断するような形)の天井に遊具のうんていを取り付けている家が紹介されていました。 家に遊具を付ける場合の法的基準などはあるのでしょうか?
- 基本的に遊具というのは建築基準法の領域です。レジャー施設も幼稚園のブランコも建築基準法に則って作成されております。ベランダなどの屋外に関する制限はそれなりにありますが、室内同士の落下などに関する規定は建築基準法ではそれほど厳しくなく、設計者の判断に任されているというのが実情です。
- 基礎断熱であれば、床下の環境は大事だと思います。 そこで耐圧版式グリッドポスト基礎工法という工法を知ったのですが、空気の流れが良くなりそうで床下エアコンの効きも良くなりそうと思うのですが、耐久性や耐震性の面でご意見を伺いたいです。
- 基礎は構造物です。
設備である床下エアコンと構造である基礎のどちらが大事かと言えば、言うまでもなく基礎です。床下エアコンの為に、基礎の構造を無理のある物に変えるというのは、建築を志す物としては優先順位を間違えた非常に筋が悪い事だと、私は思います。強い段ボール箱を作ろうと思ったら、底面だけハニカム式の分厚い物にして壁の数面が開いているものよりも、しっかりと4面に壁がある方が合理的で省コストです。普通の基礎の間をちゃんとエアコンの風が行き渡る様にするのが設備設計者の腕です。