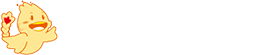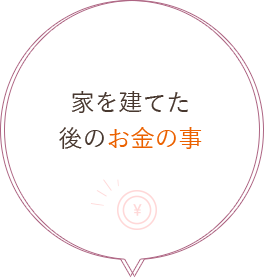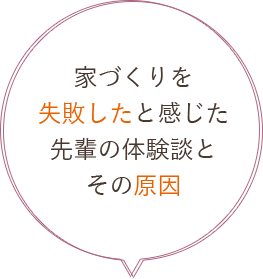Q & Aよくある質問
よくいただくご質問をまとめました
気密・断熱について
- 屋根断熱をする際に、ダンボール製の通気部材にアイシネンを吹き付けするのは通気層の確保に問題ないでしょうか? また、基礎内断熱の断熱材として基礎部分に直接アイシネンを吹き付けるのは長期的な性能維持も含めて問題ないでしょうか?
- 屋根に関してはよく行われるやり方です。施工する職人さんの匙加減で段ボールが通気層側にどれだけ膨らむかが決まりますので、これは職人さんによるというのが答えになります。基礎についてですが、こちらもよく見かける気がしますが、形状が単純である基礎は、ボード状の断熱材を施工した方が厚みの確保や断熱材の質の確保もしやすいと思いますので、わざわざ現場吹付を行わない方が良いのではと思ってしまいます。長期的な性能も問題かもしれませんが、基礎の場合は防湿フィルムの施工がなされない例が殆どですので、湿気の出入りは有ります。
- 気密テープは地震で剥がれたり破れたりしないんでしょうか?
-
構造が柔らかいと破れます。
そのため、耐震等級3の硬い構造と高気密高断熱はセットで必須なんです。
- 気密C値0.3以下の家がいいと思うのですが、気密C値0.3に慣れてないハウスメーカーでは実現は難しいのでしょうか?
-
ハウスメーカーや建売の下請け工務店さんが、まっとうなC値0.3が出せるとは思えません。
C値0.5を切ろうと思うと、施工だけでは難しく、設計段階からの工夫や素材の選定にも気を使います。その知識が無い人が設計をすると、やはりC値0.3という値は出てきません。
- 名古屋圏でC値が0.5、UA値0.46の場合、窓をペアガラスからトリプルガラスに変えても費用対効果はありますか?
- 何を持って費用対効果とするかにもよります。例えば、光熱費と初期コストの2点だけを考慮すると、ペアガラスの方が割安になる可能性も十分にあります。しかし、ペアガラスでは窓のそばで冷気を感じる為、その近くには寄りたくないなと思ってしまうと、窓の周囲が使えない空間となり、家が実際より狭い事になってしまいます。ハニカムサーモスクリーンの様に断熱を更に補強する部材を取り付けた際、ペアガラスでは雫が垂れるほどの結露が起こる可能性もあります。結露を起こさずスクリーンを使えるトリプルガラスの断熱性能vs結露が起こる為サッシだけのペアガラスの断熱性能となると、光熱費、快適性が更に変わってきます。直接的なコストの他に、間接的に変わって来る部分もありますので、いただいた条件で、可能であれば窓はトリプルガラスにしておくことをお勧めします。予算が無ければ、洗面や浴室、など、温度が低く湿度が高い水回りだけでも変えておかれると結露の量はてきめんに少なくなります。10年後、周囲の家でトリプルガラスが当たり前になった時、自分もこうしておけばよかったと思わないと言い切れるならペアガラスでも良いかと思います。
- 床断熱+天井断熱の家と、基礎断熱+屋根断熱の家だと気積が結構違うと思います。温熱環境の面で気積の大小による有利・不利などありますでしょうか?
- 非常に鋭い質問ですね。おっしゃるように、基礎/床、天井/屋根で気積が変わってきますので、例えばC値を測定する時の分母が変わってきたり、UA値を計算する時の外皮面積が変わってきたりします。一般的には分母が大きくなればなるほど、係数は下がりますので、床断熱+天井断熱の家よりも、基礎断熱+屋根断熱の家の方が、UA値やC値は下がりやすいです。ただ、それらの係数は下がっても、隙間の絶対値や、熱が逃げる外皮の絶対的な面積は増えておりますので、光熱費は基礎断熱や屋根断熱の方が増える事になります。屋根断熱をするのであれば、小屋裏空間を上手に使って、勾配天井や、ロフト部屋を有効活用しないと勿体ない事になってしまいます。参考にしていただければと思います。
- 気密性能ですが、最低でもC値1.0がよいと言われる方が多いと思いますが、30年〜50年後でも同じ気密性能を保てるのでしょうか? もし三種換気などで気密性能が落ちてしまうと当初の換気計画通りにならなくなるかと思います。また、気密を落とさない工夫や落ちた場合の対処方法はありますか?
- 気密性を落とさないためにはいくつかの方法が有効です。まず耐震性能を上げる事です。家を固く作り、細かい地震ではびくともしないような構造にしておくことで、気密性能の低下は防ぐことが出来ます。
次に外張り断熱を併用する事です。構造材の収縮も気密性を落とす大きな要因ですが、外張り断熱の家の場合は温度変化による木材の収縮を大きく減らすことが出来ますので、気密性能の劣化は少ないです。
次に含水率の低い木材を使う事です。施工後に木材が痩せるのを防ぐことが出来ます。最後に、細かい振動から有効な制振材を使う事です。大地震の時だけではなく、小さな地震から効果を発揮する制振材を使う事により、構造の変位を抑える事が出来ますので、結果として気密性能が落ちにくくなります。気密性能が経年によりどの程度落ちるか、どんな原因で落ちるかという事は1990年には既に北海道工業大学の研究室にて実測された研究結果が論文発表されております。上記の対策を全て講じた場合、気密性能の低下はほぼ発生しないと思っていただいて大丈夫です。
- 玄関扉の郵便受けは気密性から考えるとつけるべきではないように思いますが、郵便は外に取りに行くしかないのでしょうか? 気密性を維持しながらの方法って何かありますか?
- 玄関ドアに郵便受けが付属している商品ではお勧めできるものはありません。ただ、キョーワナスタさんが壁付けの断熱気密タイプの郵便受けを発売しております。ただ、高断熱住宅に使用しないと断熱性確保は難しい可能性があります。
- ボード気密の場合、内側の防湿シート上で気密コンセントボックスの施工は必ずしも必要なくなるのでしょうか?
-
ボード気密の場合でも防湿シートの連続は必須ですので、気密コンセントボックスは必要です。
- 基礎断熱で、床下エアコン等の床下を温める手法を取らない場合、床は冷たくなってしまうでしょうか?絨毯などはあまり使用せず、無垢床を素足で過ごすのが夢なのですが。断熱性はG2程度を想定しています。
-
引っ越した当初に寒さを感じる事は無いと思います。恐らく足元環境も含めて今までよりもはるかに暖かい環境が手に入るはずです。
ただ、床下に熱源のある家と比べてしまうと、暖かさの差は次第にはっきり感じ取れるようになっていきます。床下に熱源の無い家の場合、床の冷たさを決めるのは気密性と窓からのコールドドラフトになります。樹脂サッシを使ったG2とアルミ樹脂複合サッシを使ったG2では足元の暖かさは全然違うという事です。人間の足の冷たさセンサーは引っ越し以降どんどん繊細になっていきますので、2年目、3年目と住むにつれて、なんだか寒くなってきたという感想を抱かれるかもしれません。
- ハニカムスクリーンの断熱レールはあった方が良いでしょうか?レールありの方が断熱効果は高いと思いますが、結露予防の為に少し開けて使用するという実情も聞きまして、レールの意味があるのかなと迷っています。
- どの地域に建てるか、窓の商品は何か、家の中をどのような温度湿度で生活するかによって答えは変わりますので何とも言えませんが、弊社の場合は、レールがあったほうが良い様な設計施工を致します。寝室や脱衣所の窓で、ガラス縁あたりに出来る雫が垂れ落ちない程度の結露は発生しても問題ありません。