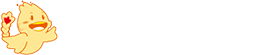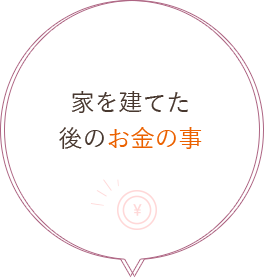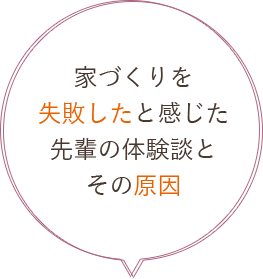Q & Aよくある質問
よくいただくご質問をまとめました
気密・断熱について
- 可変調湿気密シートの長期耐久性ってどうなのでしょうか?そもそも、気密シート無しでも内部結露しない壁構成が必須のように思えるのですが。
-
こちらは、私も同様の問題意識は持っておりますが、現状では分からないというのが正直なところです。一般的に物質の劣化原因は、熱、水、紫外線になりますが、そのうちの熱と紫外線から守られているのが気密シートの施工位置になります。残りの、水による劣化がどの程度なのかは耐久性試験の結果からも分かりにくい商品が多く、ひょっとするとやはり30年に1度はめくらないとダメな物かもしれません。
気候変動により結露が冬型から夏型にわずかずつではありますがシフトしてくることを考えると、また新たな壁体構成を考えていく必要が出てくる可能性も否めませんね。
勿論、防湿フィルムレスの構造を考えることも一つの回答だとは思いますが、それは防湿フィルムを使うよりももっと高等技術ですので、イメージだけで安易にやってよい物ではありません。
- 気密測定を普段しない工務店は、ドアを閉めた状態で薪ストーブの火がつきにくい、シンクの水が流れにくい、ドアが開いたらスムーズに水が流れるから気密測定しなくても高気密住宅と言いますが合っていますか?
-
絶対にダメだとは言いませんが、私の周りにはそういう工務店はおりません。模試を一回も受けたことは無いけどもクラスの中では頭が良い方だから東大合格間違いなしと言っている受験生をどこまで信用するかみたいなものでしょうか。
- 半外付けサッシを使用する場合、湿式外断熱工法が交換後の補修もやり易いような気がしますがどうでしょうか?ユーロサッシも検討してのですが、あまりに高すぎるのと台風が強い地域なので内付けサッシに抵抗があります。
- 私が半外付けのサッシを施工する際は、あえて付加断熱を2段階処理にして、後からでも何とか交換できるようにとは考えて施工をしております。
そうですよね、輸入サッシ、価格が跳ね上がりますよね。
私が半外付けのサッシを施工する際は、あえて付加断熱を2段階処理にして、後からでも何とか交換できるようにとは考えて施工をしております。
EPS断熱材は切り貼りもしやすいので、おっしゃる通りそれらの工法も後からやりやすい物の一つではあると思います。
ただ、贅沢を言えば、EPS断熱材による湿式外壁は、ヨーロッパの様に、厚みを15cmとか20cm取る事に真価が発揮されますので、厚さ数cmの日本のやり方はちょっともったいないような気も致します。
この辺の試行錯誤は終わりがありませんね。
また、内付けサッシが台風によって漏れるという事はしっかり施工していればありませんが、内開きサッシはあまりに強い風と雨を受けると、ほんの少し、水が家の中に入ってくることはあります。内開きサッシを取り付けられる場合は、台風の日に、窓の下にスポーツタオルを敷いておくと良いかもしれません。
- 基礎外断熱についてどう思われますでしょうか?
- 弊社の場合は基礎外断熱2割、基礎内断熱8割、床断熱が100件に1件あるかどうかという割合になります。
弊社の場合は基礎外断熱2割、基礎内断熱8割、床断熱が100件に1件あるかどうかという割合になります。会社の社屋は基礎外断熱にて建てられた20年前の木造建築物になります。特に白蟻にやられたという事は有りません。
やはり、リスクが高いという点は認めざるを得ないと思います。
ただ、断熱性能を突き詰めて考えていくと、基礎内断熱による熱橋は無視できない物になっていきます。UA値が0.3前後の建物であれば基礎内断熱でもいいかなという気が致しますが、UA値が0.2前後の建物を目指すのであれば、基礎の熱橋が惜しいなと感じます。(詳しくは計算です)
基礎外断熱を安易にやり始めた人が事故を起こしたので、悪いイメージが付きまといますが、昔から断熱に取り組んでいる人がきちんと施工した基礎外断熱で蟻害が大変な事になったというのはあまり聞きません。
- 高気密高断熱の家に住むとアレルギーが改善されたり健康寿命が延びるなどのデータがあると思いますが、例えば日本より住宅性能基準が高い海外では日本以上に健康改善や健康寿命が延びているんでしょうか?またそういったデータを見れるサイトはありますか?
- 最も有名なのはイギリスが実施した大規模国民調査ではないでしょうか。
最も有名なのはイギリスが実施した大規模国民調査ではないでしょうか。
また、一昔前に良く言われた、スウェーデンでは、お医者さんに掛かると「どんな家に住んでいますか」と聞かれるというのは、20年くらい前までは当たり前にあったようです。その後、暖かい生活が当たり前になってからの世代は聞かれたことが無い人の方が多いようです。
データが見られるサイトとなりますと、外国語ですので何ともですが、ちょっと調べれば各国の室温を比較してプロットされた世界地図データなどはすぐに出てきますね。
岩前先生の論文は普通に検索すればダウンロードできます。
- これから住むのが30年以内ならG1がコスパ的にもベストとお聞きしましたが、ランニングコストの面からみても、少し無理をしてG2グレードにしておくのはやはり無駄なのでしょうか?
-
30年以内なら生涯コスト的にG1がベストというのはその通りですが、あなたが建てた家はあなたが亡くなられた後はどうなりますでしょうか。
戦争が終わって以降、日本人は自分の事だけを考えて家を作ってきました。その結果が今の空き家問題です。G1に満たない家を作るよりははるかに良い事だとは思いますが、自分の家を受け継いで住む人たちの事を考えてみるのはいかがでしょうか。
また、G1でいいやという家にしますと、水回りの窓が割と高い確率で結露致します。樹脂窓を使わなくても建てられるからです。
毎日の生活の豊かさはG1とG2、またそれ以上になった場合も全然違ってきます。昨日も兄弟で集まり、等級4の家に住んでいる人、G1くらいの家に住んでいる人、G2くらいの家に住んでいる人、G3くらいの家に住んでいる人が家に対する感想を言い合いましたが、この時期の寒さに対する感想は全く違っていました。
- 玄関ドアについての質問です!片開きドアと親子開きでは気密性能はかなりの差がありますか
- かなり、の定義は人それぞれで曖昧ではありますが、
かなり、の定義は人それぞれで曖昧ではありますが、親子ドアですと、気密は0.05cm2/m2程度落ちると考えて頂いても良いかと思います。JIS的には0.1cm2/m2落ちるかどうかという所です。
- 可変防湿気密シートという物は、梅雨時期に壁全体から湿気が入ってきてしまうのではないかと思ったのですが、エアコンを上手く使えば、コントロールできる範囲のことなのでしょうか?
-
これも非常に微妙なところですね。夏型壁体内結露を起こしてしまうくらいなら、まだ室内に湿気を流入させた方が良いと思いますが、それでも暑い時期には1日に1リットル~の湿気流入が起きる可能性があります。26℃60%程度の環境で良ければ、そんなに気にしなくても大丈夫ですが、夏に40%台の湿度をと考えると、可変防湿シートが少しネックになってきます。どんな室内環境を作りたいかどうかで、最適な壁体構成も変わってきます。
- 耐震等級3、高気密高断熱にすると一階の南側窓面積が小さくなると聞いたことがありますが本当ですか?
-
本当です。窓は断熱的にも耐震的にも弱点になります。無制限に窓を付けて耐震等級も3が取れるという事はありません。特に、南北に長い建物になる場合は、1階の南側の窓は思うように取れないことが多いです。
高気密高断熱にする事と、窓が小さくなることは関係がなく、耐震等級3を取ることだけが窓の大きさに関係してきます。
ただ、この手の話が、間違って伝わりやすいのは、質問者さん含めて殆どの方が、数字を入れずに話をするからです。例えば、南の間口7mに対して、耐震等級2であれば窓部分が4m壁部分が3mのバランスが可能だったのが、耐震等級3にすると、窓部分が3m壁部分が4mのバランスになりますなど、具体的な数字を入れないで「大きくなる、小さくなる」「思うように窓が取れない」という定性的な話をしてしまいますと、答えている人は、全面ガラス張りは流石に無理というイメージで話しているけども質問している人は、人の頭も出ないような窓しかつかないと受け取っているなどの齟齬が生じます。
具体的な質問には具体的な答えが返せます。抽象的な質問には抽象的な答えしか返せません。
質問者さんが思う南側の窓の大きさが分からない以上、答える側としては安全側を見て「窓は取れない」と答えるしかありません。
- 部屋干しで布団が乾くことで布団のダニのリスクは低くなるのでしょうか?
-
ダニの繁殖は夏場の高温高湿な状態で活発になりますが、そもそも家全体が高温高湿にならなければダニの繁殖は非常に抑えられます。
勿論湿った布団もすぐに乾くためベッドに敷きっぱなしで大丈夫です。
どうしても気になるようであれば布団乾燥機やレイコップを使っても良いですが、殆どの家庭で、そういったことは全く気にせずお過ごしいただいております。性能不足、換気不足の家では室内の空気環境は非常に悪いものになりますが、適切な性能を持った建物で適切な空調を掛ける事により、とても衛生的な生活を送る事が可能です。
目安として夏場は28℃以下湿度60%以下(絶対湿度14g/kgDA以下)で過ごすようにしていただければ大丈夫です。
地域の気候によっても違いますが1日に約20リットルの水分を室内から室外に捨てると上記のような環境が実現します。
温度はともかく、湿度を下げるのは家の性能や設備の選定がしっかりしていないと非常に大変です。
しっかり計算してくれる建築会社さんをさがしていただければと思います。