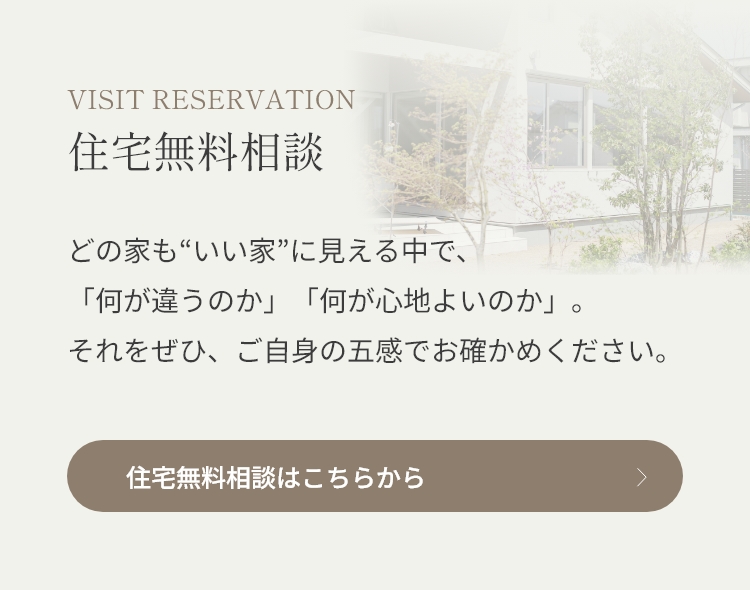QUESTION Q&A

よくある質問
- これから住むのが30年以内ならG1がコスパ的にもベストとお聞きしましたが、ランニングコストの面からみても、少し無理をしてG2グレードにしておくのはやはり無駄なのでしょうか?
-
30年以内なら生涯コスト的にG1がベストというのはその通りですが、あなたが建てた家はあなたが亡くなられた後はどうなりますでしょうか。
戦争が終わって以降、日本人は自分の事だけを考えて家を作ってきました。その結果が今の空き家問題です。G1に満たない家を作るよりははるかに良い事だとは思いますが、自分の家を受け継いで住む人たちの事を考えてみるのはいかがでしょうか。
また、G1でいいやという家にしますと、水回りの窓が割と高い確率で結露致します。樹脂窓を使わなくても建てられるからです。
毎日の生活の豊かさはG1とG2、またそれ以上になった場合も全然違ってきます。昨日も兄弟で集まり、等級4の家に住んでいる人、G1くらいの家に住んでいる人、G2くらいの家に住んでいる人、G3くらいの家に住んでいる人が家に対する感想を言い合いましたが、この時期の寒さに対する感想は全く違っていました。
- 天井の断熱性能(部材、厚さ)の標準はどれくらいですか?
-
物件によってバラバラですので標準の断熱性能というのはありませんが
現在進行中の現場ですと、R値6.3㎡K/W(高性能グラスウール16Kで240mm相当)が最低で、R値15㎡K/W(高性能グラスウール16Kで570mm相当)というのが最高です。住まい手が求める広さ、温熱環境、冷暖房費、生活スタイルから性能を逆算して決めております。あなたがこうありたいと願う暮らしを実現させるために必要な断熱の厚みを提供します。
- 高気密高断熱住宅は乾燥すると聞くのですがなぜでしょうか。一般住宅との違いを教えて頂きたいです。
-
一般住宅よりも同じ暮らしをしていても温度が上がるからです。温度が上がれば相対湿度は下がりますので、乾燥している様に感じます。
それだけの理屈になります。
- 現在、家づくり検討中です。その中で付加断熱をしたいと考えてるのですが、付加断熱材でおすすめなどありますでしょうか?付加断熱も充填断熱同様、施工性や施工工務店で使い慣れているものやコスパで考えればいいのでしょうか?
-
断熱材の選定ポイントは、地域の特性に合っているか、やりたい生活に合っているか、土地の状況に適っているかで決めておりますが、その工務店さんの得意なものがあれば、それでお願いしても良いかと思います。
火事が心配な地域なら火を通しにくい断熱材が良いでしょうし、水害が想定される地域なら発泡系の方が復旧は早いです。ケースバイケースで、弊社も使い分けております
- 凰建設では準防火地域の家を建てる際にも、HEAT20のG3クラスの家を建てるのが最終的に最も良いと考えられているのでしょうか?一番性能の良いトリプル樹脂や高気密高断熱の玄関ドアを使用すると防火性能が落ちるため、屋根・壁・床の断熱性能を上げてカバーするのでしょうか?
-
難しい問題ですね。準防火地域では弊社の場合ですと、外側に防火サッシ、内側には内窓という形で性能を上げていくことが多いです。そうすると特に無理なくG3クラスの家は建てられます。
それも人それぞれだとは思いますので、性能を決める際は、どんなところが落としどころになるのかを、住まい手さんとディスカッションしながら決めております。
準防火地域でUA値0.19W/m2・Kみたいな事に落ち着く家もあれば、0.4W/m2・K程度になることもあります。
これまでにいただいた質問
- 壁及び床下断熱で木熱橋をなくすためにはどのような構造にすべきなのでしょうか?
-
床も壁も付加断熱にすれば木熱橋は少なくなりますし、断熱材をボード系の物にすれば更に熱橋は少なくなります。
- 貴社では壁の断熱について、内付加断熱と外付加断熱それぞれの場合でどのような熱橋対策をされていますか?
-
弊社の施工エリアの特性上、内付加断熱を施工することはほぼありませんので、外付加断熱の場合での熱橋対策についてお話致します。
外付加断熱を施した場合、熱橋になりえる部分というのが非常に少なくなりますので、残りは窓周りの線形熱橋や、天井断熱と壁断熱の境界部や基礎断熱(床断熱)と壁断熱の境界部などの線形熱橋対策がメインとなります。窓はなるべく内付け納まりにしていく事、断熱材が土台や桁を包むように施工する事が最も効果の大きな対策になります。
イメージとしては構造の木を外気の熱に晒さない。全部断熱材で包むといったイメージとなります。
- 基礎断熱で、床下エアコン等の床下を温める手法を取らない場合、床は冷たくなってしまうでしょうか?絨毯などはあまり使用せず、無垢床を素足で過ごすのが夢なのですが。断熱性はG2程度を想定しています。
-
引っ越した当初に寒さを感じる事は無いと思います。恐らく足元環境も含めて今までよりもはるかに暖かい環境が手に入るはずです。
ただ、床下に熱源のある家と比べてしまうと、暖かさの差は次第にはっきり感じ取れるようになっていきます。人間のセンサーが敏感になってくるからです。床下に熱源の無い家の場合、床の冷たさを決めるのは気密性と窓からのコールドドラフトになります。エルスターXやAPW430(→樹脂サッシ)を使ったG2とエピソードやサーモスⅡH(→アルミ樹脂複合サッシ)を使ったG2では足元の暖かさは全然違うという事です。
人間の足の冷たさセンサーは引っ越し以降どんどん繊細になっていきますので、2年目、3年目と住むにつれて、なんだか寒くなってきたという感想を抱かれるかもしれません。
- UA値0.34の家でも0.30の家でも、仮に両者の計算上の冷暖房費が同じなら、快適性も同じなのかと思っていたのですが、体感温度は室温だけではなく、周囲の表面温度で決まるという事を知りました。その事を考慮した場合、連暖房費が同じでもUA値0.30の家の方が体感温度的に快適になりますか?
-
仰る通り、UA値が下がれば下がるほど、家の中の環境は快適になります。一般的に家全体を暖める暖房方式の場合、住宅の中央部分ほど快適性が高く、窓や外壁に近づくほど不快感が高まります。
中央部分は部屋の室温もその周りの間仕切り壁も家の中で最も高い温度になっております。逆に窓周りなどは家の中でも最も低い温度になっております。この温度差が体感温度を下げる原因になります。UA値が下がるほどに窓の部分や外壁部分の温度低下度合いが下がりますので、家中の温度が均一に感じられやすいという仕組みになります。
余談ではありますが、窓の性能がものすごく高い物を使い、壁の断熱が程々のUA値0.34の家と、壁がものすごく性能が良くて、窓の性能が程々のUA値0.30の家を比べると、0.34の家の方が暖かく感じるという事が起こり得ます。この場合はUA値0.34の家の方が家中満遍なく同じ温度になり、UA値0.30の家は窓の周囲だけ極端に冷えますので、温度ムラが大きいという意味で、0.30の家の方が寒く感じられるという事になります。
UA値を上げる目的は、光熱費を抑えるという事もありますが、家の中の環境を穏やかで優しいものにするためという意味合いも大きいです。是非、UA値が0.87の家から0.20くらいの家までを真夏や真冬に体感して違いを感じてみて下さい。
- いつもメルマガで勉強させて頂いています。芥見南山パッシブハウスなど、窓や扉は比較的凡庸なものなのに、高い性能で驚きます。やはり、まずは壁や屋根の断熱、と考えるのが正解ということでしょうか。
-
芥見南山パッシブハウスの窓や扉ですが、Uw値が0.8前後と、国産の最上位窓と同じかそれ以上の性能の物を使っております。決して窓を疎かにしているわけではありません。
ちなみに日本の一般的なアルミペアガラス窓は4.66になりますので5倍の性能という事になります。
グラスウールを申し訳程度に入れた壁で同じく壁のU値が0.8程度になります。
南山パッシブハウスの壁のU値は0.15程度です。という事を前提にお話しますが、一般的に家の外皮における窓面積の割合というのは5%前後になります。外皮の断熱性能を表すUA値は、全ての断熱構造の平均値になります。今までは壁の断熱性能に比べ、窓の性能が1/5くらいしかなかったので、5%程度の面積の窓から入ってくる熱が家全体の3割以上になり無視できない値になりましたが、十分に性能の高い窓は、家の性能にそこまで影響することはありません。少しずるい話になりますが、窓が全くない家を設計しますと、グラスウール100mm程度の断熱でもUA値が0.4を下回り、G2グレードの家になります。
順番的には、まず窓の性能をUw値1.5以下の物(LIXILのエルスターSやYKKのAPW330相当)にする事、そのあとは窓よりも屋根や壁を中心にU値0.2以下(グラスウールで200mm)を目指す。両方超えたらまた窓をUw値1.0以下の物に変えていくというのが今のところの順番ではなかろうかと思います。
家の性能向上はボトルネックをつぶしていく作業です。高性能な家のどこかに大きなボトルネックがあると、痛みがそこに集中するからです。
また、パッシブハウスクラスまで行きますと、既製品の窓の性能限界が来てしまいますので、後は壁や屋根で性能を上げていくしか方法がないというのもあります。