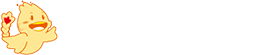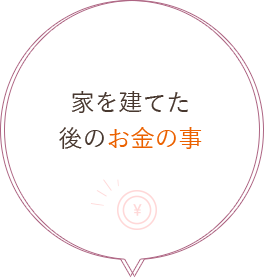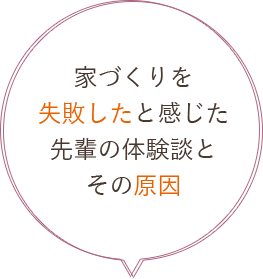Q & Aよくある質問
よくいただくご質問をまとめました
気密・断熱について
- 貴社では壁の断熱について、内付加断熱と外付加断熱それぞれの場合でどのような熱橋対策をされていますか?
-
弊社の施工エリアの特性上、内付加断熱を施工することはほぼありませんので、外付加断熱の場合での熱橋対策についてお話致します。
外付加断熱を施した場合、熱橋になりえる部分というのが非常に少なくなりますので、残りは窓周りの線形熱橋や、天井断熱と壁断熱の境界部や基礎断熱(床断熱)と壁断熱の境界部などの線形熱橋対策がメインとなります。窓はなるべく内付け納まりにしていく事、断熱材が土台や桁を包むように施工する事が最も効果の大きな対策になります。イメージとしては構造の木を外気の熱に晒さない。全部断熱材で包むといったイメージとなります。
- 壁及び床下断熱で木熱橋をなくすためにはどのような構造にすべきなのでしょうか?
-
床も壁も付加断熱にすれば木熱橋は少なくなりますし、断熱材をボード系の物にすれば更に熱橋は少なくなります。
- APW430とAPW330+ハニカムサーモですとコストと性能は同等になりますか?
- APW430の熱抵抗は1.10㎡K/WAPW330の熱抵抗は0.76㎡K/Wハニカムサーモは0.26㎡K/Wになります。(レール無し)APW330+ハニカムサーモ=0.76+0.26=1.02㎡K/Wとなり、APW430単体にまあまあ迫る性能数値になります。コストはそれぞれの建築会社さんによって変わりますので、実際に見積もりを出してもらって比較されると良いと思います。小さな窓なら430単体、大きな窓なら330+ハニカムサーモの方が安くなるような気がします。
- 気密を考えた場合、窓は少ない方が良いと考えておりますが、風呂場、トイレの窓は必要だと考えていらっしゃいますか?またその形状は採光のためだけならFIXが良いのでしょうか?
- 私個人としては不要と考えておりますが、これもヒアリングをした際、お客様の希望によってつけるかどうかは変わります。開く窓をつける方、FIXを付ける方、様々です。お風呂は清掃の事を考えると窓無しもしくはFIXがいいのではないかと思います。ただし、これも本当に高性能な家になっている事が前提ではあります。
- 将来使用する可能性があり、居室に開けてあるエアコンのスリーブの気密処理はどのように行いますか?
-
市販のスリーブ部材を使って気密処理をすればOKです。
新築のスリーブ処理となんら変わりません。スリーブの空胴部分にはグラスウールなどの断熱材を入れておけば大丈夫です。
- 断熱について、窓、壁、屋根、の断熱性能を上げるのに優先順位はどれが一番高いでしょうか?
-
一般的に家の外皮における窓面積の割合というのは5%前後になります。外皮の断熱性能を表すUA値は、全ての断熱構造の平均値になります。今までは壁の断熱性能に比べ、窓の性能が1/5くらいしかなかったので、5%程度の面積の窓から入ってくる熱が家全体の3割以上になり無視できない値になりましたが、十分に性能の高い窓は、家の性能にそこまで影響することはありません。少しずるい話になりますが、窓が全くない家を設計しますと、グラスウール100mm程度の断熱でもUA値が0.4を下回り、G2グレードの家になります。
順番的には、まず窓の性能をUw値1.5以下の物(LIXILのエルスターSやYKKのAPW330相当)にする事、そのあとは窓よりも屋根や壁を中心にU値0.2以下(グラスウールで200mm)を目指す。両方超えたらまた窓をUw値1.0以下の物に変えていくというのが今のところの順番ではなかろうかと思います。
家の性能向上はボトルネックをつぶしていく作業です。高性能な家のどこかに大きなボトルネックがあると、痛みがそこに集中するからです。また、パッシブハウスクラスまで行きますと、既製品の窓の性能限界が来てしまいますので、後は壁や屋根で性能を上げていくしか方法がないというのもあります。
- 床下エアコンを採用しない場合の、基礎断熱にするメリット、デメリットを教えてください。
-
ご存知かとは思いますが、床下エアコンと基礎断熱であれば、基礎断熱の方が歴史は古く、床下エアコンの為の基礎断熱という事ではありません。なので、普通の基礎断熱のメリットデメリットを申し上げます。
基礎断熱のメリットは、床下空間の乾燥が保たせやすい為、土台や大引きといった、床下の構造材が劣化しにくい事にあります。また、基礎の空間が使える為、床下収納等が作りやすい事も挙げられます。ユニットバス部分で熱橋が出来にくい等もあります。基礎外断熱の場合は、基礎コンクリートの持つ熱容量(熱を蓄える力)を家の性能に組み込むことができます。
基礎断熱のデメリットは、基礎外断熱の場合、シロアリの被害が分かりにくい事、床下の空間を「汚いもの」とイメージされる場合は、その空気を吸い込むことに抵抗がある事、断熱計算の際、基礎空間のボリュームも容積に含まれるため、若干冷暖房する容量が増える事です。
- 床下断熱を採用する場合でも、土間、ユニットバスは基礎断熱になると聞きましたが、どのような断熱材をどの程度の厚みで入れることが、基本となりますでしょうか?
- 他の部分の床断熱材と断熱レベルを合わせていく事が多いと思います。床断熱がスタイロフォームの50mmだとしたら、基礎も同じく50mm。床がグラスウールの90mmだとしたら、吹付のアクアフォーム80mm等です。入れない場合や外周から1mの範囲でしか入れない建築会社さんもいますが、効果が薄いので気を付けてください。
- 床下断熱とする場合、断熱材はどのくらいの厚みまで施工できるものなのでしょうか??フェノバボードなどをできるだけ厚く施工できればと考えています。
- 基本的に厚みについて制限はありません。床下空間の500mmくらいを全て断熱材で埋めてしまったという家も世の中には存在致します。ただ、現実的な話を致しますと、大体土台の厚み(105mmとか120mm)くらいまでが一般的になります。それを超えてくると床下の空間の確保という問題が出てきます。長期優良住宅に相当する建物だと、床下空間は330mm以上確保する必要が出てきます。分厚くするほど基礎を高く設計していく必要が出てきます。また、天井や壁よりも、床の方が熱の移動が少ないですので、壁で120mmの断熱材を入れるのと、床で85mmの断熱材を入れるのはほぼ同じくらいの熱の逃げ方になるというのが建築基準法の考え方になります。建物に必要とされる性能から逆算して床の断熱仕様を決めていく事が望ましいと思いますので、どれだけが可能かというよりも、どれだけ必要かから、床の構造を決めたほうが良いかと思います。最後に、床暖房を施工する場合は特に床の断熱材にこだわる必要があります。床暖房の熱が床下に逃げないように出来る限り断熱を厚くしないと、床暖房の効率がどんどん落ちていき、非常にランニングコストの高い暖房になってしまいます。
- 気密測定の時期、回数、その際に気をつける点について、どのようにお考えでしょうか?
- 理想を言えば気密施工完了時と入居前の2回行いたいです。弊社は2回やっておりますが、気密施工には大体1回あたり5万円~10万円のお金がかかりますので、住まい手さんがそれを良しとするかも大きなポイントです。よくやりがちだけど絶対やってはいけないのが、窓の目張りです。特に引き違いを目張りすると極端に上振れした値が出ます。0.5を下回ってくると、漏気はほぼ窓からになります。0.5までは施工、0.5からは窓の選定が気密を下げるポイントになります。