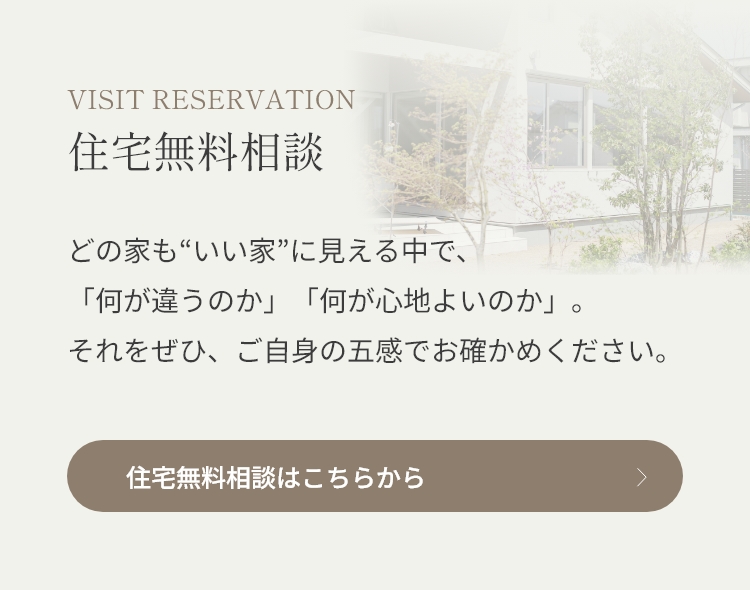QUESTION Q&A

よくある質問
- 第3種換気を検討しています。静圧等の圧力制御の性能はどの程度を考慮する必要がありますか?その他スペックで確認した方が良い項目も教えていただければ幸いです。
-
換気扇の静圧はこだわった方が良いのですが、断熱の方がまずは優先ですし、これは住まい手はおろか、ほぼ全ての設計者はどのように数値を確認して設計に生かしてよいかは分かりません。換気扇の静圧で商品を選んでいる人は1000人に1人程度の割合じゃないでしょうか。
まずはしっかり気密が取れている事、暖房時の室内の圧力分布を計算してある事、換気扇の適切な流量が計算されている事が、設計時の確認項目です。
そして、住んだ後に、概ね1000ppm以下のCO2濃度でちゃんと暮らせているかというのがものすごく大事な確認項目です。設計がいい加減でも、住んだ後のCO2濃度がちゃんとしていればそれで大丈夫です。
- 国産の3種換気の選定で将来のメンテナンスを含めて考慮すべき点はありますか?
-
普通のパイプファンであれば後々でも交換するだけで終わりますので、メンテナンス性は気にすることはありません。
ダクト式の場合は、機器本体の交換が発生しますので、必ず機器本体+αのスペースが必要になります。それが無ければ、使い捨てのつもりで採用した方が良いです。
- 中華料理屋で炒め物を週4ぐらい作ってますが、掃除を怠ると煙や油汚れはどうしても発生します。御社のような高気密高断熱住宅の、キッチン周りの間取り、換気設計、キッチンとリビングの設計の考え方を教えていただけますか。
-
その使い方でしたら、必須になるのはキッチンの換気扇は外壁面にくっついている事です。コンロ周りに勝手口や窓は無い方が無難です。オープンキッチンでも良いですが、せめて正面と側面に壁のあるキッチンにすると良いかと思います。換気扇はお掃除機能付きなどは採用せず、掃除のしやすさの1点に絞って探すと良いかと思います。タカラのホーローレンジフードなどは相性が良いかと思います。
- 第一種換気で全熱式を採用する場合、たばこの匂いは家中に広がってしまいますか?
-
また、煙草のヤニの成分などはてきめんに熱交換素子を詰まらせますので、メンテナンスの頻度はかなり高くなります。
家の中で煙草を吸うのであれば、熱交換換気やダクト式の空調は全くお勧めできません。普通の第三種換気にしておいて、吸排気のフィルターをマメに変えたほうが良いです。
- 一種のダクト式換気で、OAに電子集塵機をつけている事例を見かけるのですが、集塵機があるとダクト清掃や熱交換素子交換の頻度は下がるものですか?
-
はい、下がりますね。ただし、電子集塵機の本当に必要な地域なのかどうかはちょっと考えてみてください。
田舎の空気が綺麗なところであれば普通のフィルターで十分ということもありますので。
これまでにいただいた質問
- 外構の人工芝と天然芝の良し悪しをそれぞれどのように考えていらっしゃいますか?
-
下記のように考えております。
<人工芝>
メリット:手入れが少ない、冬でも青い
デメリット:熱い、劣化後は見た目が悪い<天然芝>
メリット:涼しい、肌触り、人口より安価
デメリット:きれいにしようと思ったら手入れに時間がかかる。ムラが出来やすいい。
- ダクトあり1種換気を絞ることで、ダクトが汚れたり熱交換をやめて風量だけにすることでカビが増える可能性はありますか?
-
風量を絞るだけであれば大丈夫ですが、熱交換を通さないバイパスモードは、季節によってはカビのリスクは発生します。
- 全熱交換換気を採用した家の燃費を計算する場合、キッチンやトイレや浴室の換気量はどのくらいの量を想定して計算するのでしょうか?4人家族ならこのくらいなど、決められた値があるのでしょうか?
-
キッチンはメーカーのカタログを見れば換気量が出ていますので、それが一日に何時間動く想定なのかを計算して換気量を平準化します。
600㎥/hの換気量を持つ換気扇を1日に2時間動かしますと、1200㎥の空気が出ます。24時間換気に置き換えると1200÷24=50㎥/hが熱交換をせずに家の外に放出されるとみなすというような具合です。
トイレやお風呂についても同様に個別換気扇の流量がカタログに載っておりますので、上記と同じ計算を致します。その換気扇を決めるやり方は、1人当たり30㎥/h、もしくは家の気積が1時間に0.5回換気されるように決められております。
そもそもという話ではありますが、このような計算をしてキッチンやトイレ、お風呂を熱交換換気の経路から外す場合、家全体の熱交換換気効率は20%~40%程度まで落ちてしまいます。これでは熱交換換気の費用対効果は非常に悪くなります。
- キッチンの換気扇(同時給排換気扇)の設置場所は、第一種換気・第三種換気関係なく外壁に近い方がいいでしょうか?
-
キッチンの換気扇ですが、省エネについてはそこまで影響があるわけではありません。
しいて言えば、壁から離れていた方がファンの圧力損失が増えて運転する為のエネルギーが若干増える事とくらいだと思います。それよりも外壁までの距離が長くなる事により、ダクトも長くなり、
中にたまる油などの量が増える方が気持ち悪いなと感じます。そのため、やはり外壁に近い方が色々と有利だと思います。
- 6地域の場合、ua値0.28で第3種換気かua値0.34で第1種換気(全熱交換型)では体感としてはどちらのほうが住み心地がいいのでしょうか?第3種換気では足元が冷えると聞きますが実際は断熱がしっかり出来ていれば部屋に空気が入ると馴染むとも聞きます。第3種換気で気密をどの程度まで上げれば住み心地のよい環境になりますか?
-
気密がしっかりと取れている家(C値1.0以下)という前提でお答えいたします。
快適性という点ではそんなに変わらないと思います。
しかし、生涯コストという点ではUA値0.28+3種換気の家の方が50年で100万円程安いと思います。勿論設計によってはもっと差がついたりそこまで差がつかなかったりしますので、お住まいになる想定期間分の光熱費やメンテナンス費の試算を建築会社に出してもらってください。
足元の寒さが気になるようであれば、どちらの場合でも床が暖かくなるような暖房計画(床下エアコンや床暖房など)を採用するとなお良いですが、どちらが良いかについては、あなたがどのくらい寒がりかという事にもよりますので、そこは建築会社さんに数値を伴うしっかりしたヒアリングをしてもらった方が良いです。
UA値は下がれば下がるほどシームレスに家の中の温度ムラ、冷暖房コストなどが良い方向に変わっていきます。
一生涯、住宅を維持管理していく中で、よりコスパが良く、より後で触りにくいのは換気設備よりも断熱材の方です。0.3を下回るまでは、断熱材だけにお金を掛けたほうがいいです。