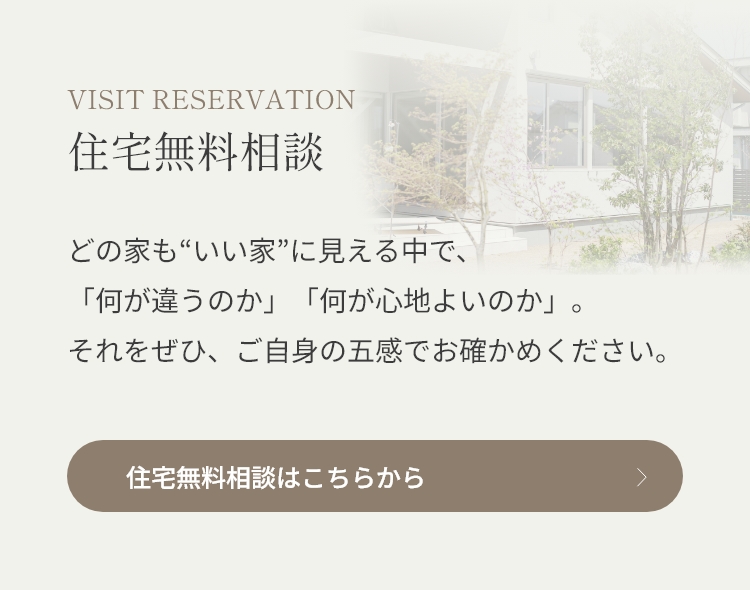QUESTION Q&A

よくある質問
- 長期的なコストや温熱環境の視点からおススメの床材はありますか?質感として、暖かく感じる材質が良いと思っています。
-
まず質感と温かみについてですが、
硬くて重い床材程、傷付きにくく、足の裏がひやっとします。
柔らかくて軽い床材程、傷つきやすく足の裏は暖かいです。前者はタイルなどが挙げられ、後者は木材です。
木材の中でもナラなどの広葉樹は硬くて重く、
杉やヒノキなどの針葉樹は柔らかくて軽い傾向にあります。また、いくら柔らかくて軽い床材を選んでも、そもそもの
室温や床の表面温度が低ければ、暖かさは感じられません。長期的なコストという点では、まず床材を「一生モノ」と
捉えるかどうかが一つのポイントになってきます。お寺の境内の床などは厚さ4cm以上の無垢材が使われますが、
あのレベルの物になりますと、少なくとも家を建てた世代の人が
死ぬくらいまでは長く持つ床になります。(紫外線や雨が当たらない前提)
建築の内装材については、一般に建物の想定使用期間と同じ耐久性を
持つ素材が、生涯コストで最も安くなる材料と言えます。勿論例外もありますが。
そういった意味では、杉の厚板は、花粉症も温熱も温かみも兼ね備えた床材と言えるかもしれません。
2階の床に関しては、耐震等級を考えるのであればどうしても24mmであったり28mmといった厚みの合板を施工することになりますので、あまり厚い床板を施工することは一般的には致しませんが、1階であれば、杉の厚板を使う施工もありなのではと思います。
今の技術の合板がどうなるかは、まだ分かりませんが、30年ほど前に施工された合板のフロア材などはどうしても合板の接着面が劣化し、人がよく歩く場所で床がたわんでしまうという例が多いです。
当時は12mmの厚みの床を1枚だけという施工も多かったので、
合板というだけの原因ではないかと思いますが、
層が剥離する可能性というのはゼロではありません。ちょっと適切な回答になっているか自信がありませんが、参考にしていただければと思います。
- 漆喰、珪藻土は調湿効果が有ると聞きますが、高性能住宅でもビニールクロスよりは梅雨時期など快適になりますか?
-
珪藻土、漆喰の調湿効果が生かされるのは中間期です。
本当に湿気の多い梅雨~8月や、水分の絶対量が少ない冬は空調(加減湿含む)無くして快適にならないのは内装材を変えても同じです。
湿気の計算をされた高性能住宅は最低限無くては話になりません。それに加えて少し湿度変化がまろやかになるのが珪藻土や漆喰になります。どちらを選ぶかという話でもありません。
- ダウンライトについて、電球交換可能なものにするべきかどうか悩んでおります。森さんはどちらを推奨されていますか?
-
今は電球交換タイプでなくても良いと思います。昔の照明は電球部分とその他の耐久性に大きな差がありましたので、電球交換は必須でしたが、今は電球部分とその他の部分の耐久性に殆ど差が無くなってきましたので、壊れたら器具ごと交換でも良いと思っております。もちろん、心配であれば電球を交換できるタイプの物にされておくのも良いと思います。
- メンテナンスコストを考えますと、屋根、外壁、樋の素材をガルバリウムに合わせるなどすることが生涯コストを押さえることにつながりますか?この場合、漆喰などは耐久性が異なるため混ぜるな危険でしょうか?
-
素材を合わせるのはメンテナンスコストを抑えるためには有効です。
ただ、壁は漆喰、屋根はガルバなど、影響の少ない混ぜ方もありますので、絶対にやってはいけないという事はありません。
屋根材の耐久性の方が上に乗る太陽光パネルよりも短いなどの例が、混ぜるな危険です。
外壁の耐久性よりも、外壁にくっつける設備品の方が長持ちするというのも残念な例になります。
- 木製玄関ドアでおススメはありますか?メンテナンスが大変だと思いますが、やはり雨で濡れにくい設計が大事になってきますか?
-
気にしていただきたいのは雨と陽当たりです。木材は雨と紫外線で変化していきますので極力雨と紫外線を当てない方が良いです。
性能がしっかり出ればどこのメーカーのものでもOKです。
ユダ木工さんやガデリウスなどを使ったことがあります。
北海道にある「ノルド」さんと言う建具メーカー
北陸のキマドさんと言う建具メーカーの玄関ドアは
機会があれば使ってみたいなと思います。ちなみにメンテナンスですが、理想を言えば、最初は細かくメンテナンスを行い、塗膜の厚さや浸透するオイルの量をぐっと増やしておくと、比較的長持ちいたします。車の塗装も傷んでからコーティングをするよりも傷む前にコーティングをかけてしまった方が長持ちするのと同じです。
これまでにいただいた質問
- 外壁として焼杉を利用したいのですが、焼杉を保つために庇や軒を延ばすのが一般的なようです。その場合、パッシブデザインの日射取得にどのくらい影響するのでしょうか?
-
南面以外の庇はどれだけ伸ばしても構いません。伸ばせるだけ伸ばすのをお勧めします。
南面の庇については、ざっくりですが庇の出幅分の0.3倍の高さくらいは陰になります。例えば1m庇が出ていたら、庇から下30cmは日が当たらないと思ってください。
その目安で図面を見て頂ければ、どのくらい影響するかは何となく判断できると思います。
焼杉が傷んでメンテにお金を掛けるのも、パッシブデザインが犠牲にされて光熱費にお金がかかるのも、結局はお金という同じ土俵、物差しでリスクを測れますので、最終的にどちらがお金がかからないかという観点で良いかと思います。
焼杉も1枚ずつ交換できるような施工方法になっていれば、自分でも焼いて交換できますので、メンテは安く済みます。
私の考えではありますが、焼杉を外壁に施工する場合は、パッシブデザインを多少犠牲にしてでも、庇を伸ばした方がいいかと思います。
- 集成材、ビニールクロス、合板フローリングとヒノキ、無垢、自然素材の家と人体にはどちらがいいです?
-
素材だけで見れば無垢の物の方が良いですが、それら内装材を良くするために構造や断熱を削るような話になるようであれば、優先順位は低いです。
- 外壁には何が良いとお考えですか?サイディング、ALCなど特に何が施主に飛び抜けてメリットが有るかわかりません。
-
飛びぬけてメリットのある物というのはなかなか難しいです。また家が建つ地域や住まい手の嗜好やDIYでメンテナンスをどの程度やれるかという事にも大きく影響してきます。
岐阜地域ですと、ガルバリウムと板張りを組み合わせるのが良い様な気がしておりますが、条件によって大きく変わります。
- 外壁について、将来的なコストを考えるとガルバリウム鋼板を推されるYouTuberが多い気がします。しかし、結局コーキングの耐久性を考えると大差無いのではないかと思っています。窯業サイディングやタイルに比べて、ガルバリウム鋼板の方が劣化しにくいなどのメリットはあるのでしょうか?
-
そもそもガルバリウムの場合はコーキングを使いません。
使うとしたら換気の穴などの開口部周りだけになります。こちらは防水の意味合いも勿論ありますが、見た目の意味合いも大きいです。
- 照明計画で、調光機能のあるスマート電球を使ったことはありますか?
-
何度か施工事例がございます。